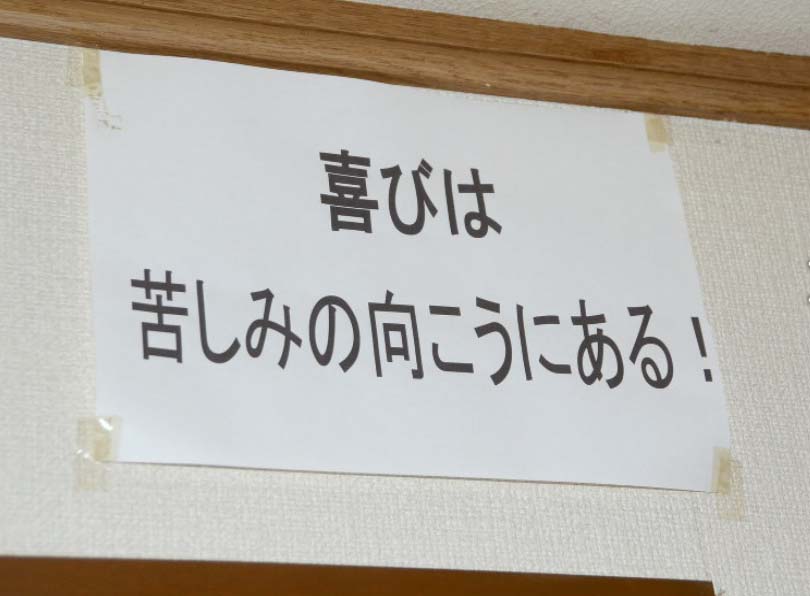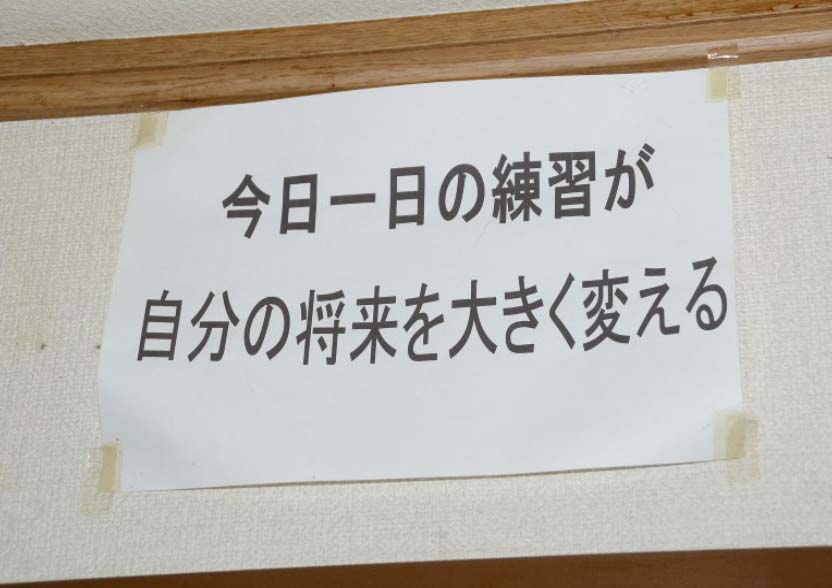2017.11.1 ストーリー
奥原希望 世界一の舞台裏 バトミントン

体がきつくて試合前半は涙が出た。中盤過ぎは太ももの裏がつりかけ、コートに倒れ込み荒い呼吸を繰り返した。8月27日、バドミントンの世界選手権(英国・グラスゴー)の女子シングルス決勝。奥原希望(のぞみ)(22)=日本ユニシス=の体力は限界に近づいていた。
相手は昨年のリオデジャネイロ五輪の準決勝で敗れたシンドゥ・プサルラ(インド)。試合時間は最終ゲームに入る時点で1時間を超えていた。でも逃げたら後悔する。自分を信じる。そう心に語りかけているうちに体が軽くなった。もっとできる。こんなもんじゃない。気持ちを高揚させた身長156センチの奥原が179センチのプサルラを巧みなショットで振り回す--。
女子ダブルスの活躍が中心だった日本バドミントン界で、奥原は女子シングルスの歴史を次々と塗り替えてきた。高校3年だった2012年世界ジュニア選手権で優勝。15年のスーパーシリーズ・ファイナルでも優勝し、リオ五輪で銅メダル。そして今年の世界選手権で金メダル。いずれも史上初の快挙だ。
痛めた右肩のリハビリの真っ最中だった昨年12月も「体を作り直すチャンス」と目の輝きは変わっていなかった。真っ暗な早朝5時に自宅周囲を猛烈な勢いで走り、右ふくらはぎを肉離れするほど体を追い込んだ。18歳の春に左膝、19歳の春に右膝の半月板損傷で手術も受けている。厳しい状況で支えにしているのは、幼少時から父圭永(きよなが)さん(58)に言われ続けた言葉だ。「迷ったら苦しい方を選べ」
頂点に立った世界選手権から帰国した奥原は宣言した。「私のゴールはここではない。東京五輪まで走り続ける」。28日で開幕まで1000日となった東京五輪を目指す奥原の、すがすがしいほどひたむきな気持ちの原点と、小さな体で世界一をつかんだ背景に迫った。
●父の熱さ受け継ぎ
バドミントン世界選手権(英国・グラスゴー)の女子シングルスで日本初の金メダルを獲得して約1カ月後の9月末。奥原希望(のぞみ)(22)=日本ユニシス=は、高校時代を過ごしたさいたま市内で後援会が開く優勝祝賀会に参加した。恩師や友人、親族らに囲まれて笑顔を見せていたが、会の直後には表情を引き締めた。「もう世界王者という実感はない。
世界選手権後の2大会ではタイトルを取れなかった。まだ絶対王者になれていない」
「2大会」とは、9月に韓国と日本で開かれた国際大会。成績は準優勝と、準決勝棄権による4強だった。周囲から見れば十分な成績だが、奥原自身は満足していない。
絶対王者。昨夏のリオデジャネイロ五輪前から、奥原がよく口にするようになった言葉だ。レスリングの世界大会で連覇を続けてきた吉田沙保里(さおり)のように「負けただけでニュースになるような選手になりたい」と言う。リオ五輪の直前も「五輪で頂点に立つ」と繰り返した。表情は真剣そのもので「わざと自分にプレッシャーをかけている。期待を背負って勝つのは難しいが、そういう選手になりたい」。
取材のたびに、真っすぐで熱い思いのこもった言葉を口にする。メモを取るこちらの手も自然と力が入る。
奥原の原点は、長野県大町市で過ごした幼少期にある。
地元出身で県立大町北高(現・大町岳陽高)の物理教諭をしていた父圭永(きよなが)さん(58)はスキー部顧問だったが、バドミントン部の副顧問も受け持つことになり、幼かった奥原と姉、兄の3人を体育館に連れて行った。隅で遊んでいた奥原も自然と小学1年くらいからラケットを握った。小学4年の時に出場した全国大会で3位に入ったことを機に、父の指導は熱を帯びていった。
小学校から帰った奥原は大町北高へ通い、高校生と約3時間打ち合う。さらに1時間半、家族だけで追加練習をした。ミスをすれば圭永さんの怒声が飛び、ダッシュ10本。練習の内容が悪ければ、自宅までの約8キロを走って帰る。圭永さんは家中にさまざまな著名人や本から拾った言葉を張った。<ちりも積もれば山となる! 小さな努力を繰り返せ!><練習は裏切らない><今日一日の練習が自分の将来を大きく変える>……。
奥原への厳しい指導を圭永さんは「中途半端にできない性分だから」と振り返る。自身は学生時代にスケート部で、スキーを始めたのは社会人になってから。だが全日本技術選手権出場を目指し、土日の練習のほか、平日も部活動の指導後、週3回のナイター練習を行い、帰宅が午後10時ごろになることもあった。全日本出場はかなわなかったが「努力の大切さは伝えてきた」と胸を張る。バドミントンの指導者になってからは、子どもたちのためにビデオカメラを二つ購入。奥原の試合と同時に、強い選手の試合を撮影して指導に生かした。大会後は奥原の試合映像を何度も見返し、得失点の原因を徹夜で分析した。
熱い思いは娘に受け継がれた。小学6年の冬、マナーの問題で圭永さんが奥原を怒ったことがある。「あんな態度を取るならやめろ。やる気があるなら態度で示せ」。すると奥原は「やる気はあります。縄跳びでいいですか」。自宅の廊下で二重跳びを始めた。途中で電話が鳴った。圭永さんがつい話し込んで時計を見ると、50分ほど過ぎていた。廊下に戻ると、奥原は苦しそうにあえぎながら跳び続けていた。「終わりでいいぞ」と声をかけられて倒れ込んだ。足はけいれんし、足裏は大きな水ぶくれができていた。圭永さんは「二度と『やる気があるのか』と問わない」と心に誓ったという。
父との練習の日々で奥原は「一つでも手を抜くと、その一日が無駄になる」と思うようになった。より良い環境を求めて、中学を卒業すると長野を離れ、埼玉・大宮東高へ進学。練習メニューを自ら作り、当時の同級生は「希望の考える内容が怖くて、学校に来ていると聞くだけで気分が悪くなる」と振り返るほどだ。チームメートに対し、トレーニング前は「過呼吸になってもいいように(呼吸を落ち着かせるための)ポリ袋を持ってきたから」と声を掛け、練習後は「今日の練習で100%を出し切れた? 強くならないよ」と問いかけた。練習後も1人で体育館に残り、監督だった大高史夫さん(66)は「強制的に体育館の照明を消さないと、練習をやめなかった」と苦笑する。
日本を代表するエースになってからも姿勢に変化はない。走るトレーニングでは、少し前にいるもう一人の自分を想像しながら、追い抜こうと全力で走る。ペース配分など一切なし。リオ五輪の半年ほど前、日本代表合宿で走り込みをした際のことだ。休憩時間に奥原の姿が見えなくなったと思ったら、トイレで吐いていた。でも「あそこまで追い込めて、うれしかった」と満足そうに笑う。
奥原が所属するマネジメント会社・スフィーダの向井久美子社長(41)は「会った瞬間から目力がビリビリ来た。何においても全力」と評する。プロ野球選手のマネジメントもしているが「野球選手は甘い。のんちゃん(奥原)の話を伝えることで、野球選手も刺激や勇気をもらっている」と語る。
奥原は休みの日も、体のケアを最優先する。区民体育館などを借りて練習することもある。「私の中でオフはない。遊びに行くのも、リフレッシュしてエネルギーがもらえると思うから。そうでないと思えば行かない。24時間365日を東京五輪のために全力で過ごす。24時間の行動をすべて公開してもいいくらい」
スポーツ漫画のヒロインのような熱いセリフを口にするが、それを現実に実行している選手なのだ。
●故障さえも成長の糧
奥原は両膝に「爆弾」を抱えている。高校3年だった13年1月の国際大会で左膝半月板を痛め、卒業後の4月に手術を受けた。半年以上のリハビリを経て、14年4月の国際大会で優勝したが、直後に今度は右膝半月板を痛めて手術をした。社会人になって本格的に世界を見据えた矢先に、続けて膝にメスを入れたことになる。ある医師は言う。「半月板を手術すれば、そこから戦いが始まる。膝に水がたまり、軟骨が変形し、腫れる」。今年9月下旬に東京で開かれた国際大会のジャパンオープンで、奥原は連戦の影響から右膝が腫れ、準決勝を棄権した。
リオ五輪後の昨年9月には右肩も痛めた。世界ランキング10位以内の選手は、世界を転戦するスーパーシリーズの中でも格の高い「プレミア」5大会を欠場すると、1大会5000ドル(約57万円)の罰金がある。「プレミア」の10月のデンマーク・オープン、11月の中国オープンと出場し続けて右肩を悪化させ、12月からリハビリに入った。公式戦からは3カ月半遠ざかった。
故障の多い印象がある奥原。しかし、サポートする理学療法士、片山卓哉さん(45)の見方は異なる。「痛みへのセンサーが鋭く、壊れる前に違和感を訴えてくれる」。奥原も「たくさんけがを経験しているので、違和感を体のイエローカードとして受け止める」と話す。
1度目の膝の手術をした後の13年9月のことだ。奥原は高校時代の恩師である大高さんに呼ばれ、片山さんの講演会に出席した。奥原は片山さんに骨盤を1分間ほど触ってもらっただけで、片足をかばって崩れていた体のバランスが整ったという。片山さんも別の高校で大高さんの指導を受けた元バドミントン選手で、全日本総合男子ダブルスで2回優勝した実績を持つ。現役時代に左足首の靱帯(じんたい)断裂の手術を受け、リハビリをしたことを機に理学療法士に興味を持ち、引退後に医療専門学校へ入った。
現在、奥原と片山さんが取り組むのは筋肉を太くする従来のトレーニングとは一線を画す。骨盤や肩甲骨などの動かし方や意識の持ち方を変えることで、スムーズな動きを高めていく。「地面を蹴るのではなく、重心移動でサーッと勝手に動く感じ」と奥原。プレーの動きから問題点を見つけると、体の構造の知識もふまえて改善方法を見いだす。再現性を高めるため、大会後には、このウオーミングアップをした時の動きはどうだったかなど検証を怠らない。学生時に数学が好きで、物事を道筋を立てて考える理系の奥原に適したやり方だ。
リオ五輪後に右肩を故障した際のリハビリ期間も、奥原は新たな試みをした。バドミントンは右腕ばかりを使うため、体に左右差が生まれる。そこで筋力トレーニングをあえてやめることで体のゆがみを整えた。故障の再発防止に重要な肩の可動域が広がり、以前はバンザイをしても右腕が耳に付かないほどだったが、それが付くようになった。
もともと、身長156センチで世界のトップクラスに立てた要因は、俊敏なフットワークと「詰め将棋のよう」と自任するショットの配球だ。相手の性格、体勢、狙いなどを判断し、2~3手先まで読みながら、1球ずつ高さ、速さと微妙に変えていく。守勢に回ってのショットも返球するだけでなく、相手を崩すための仕掛けにつなげる。さらに独自のトレーニングを重ねた結果、日本代表の朴柱奉(パクジュボン)監督(52)は「リオ五輪よりフィジカルが強くなり、フットワークが速くなった」と評する。特に前への踏み込みが素早くなり、ネット際のプレーは精度を増した。奥原は「仕掛ける引き出しが増えた。よりピンポイントで狙えるようになった」と自賛する。
今年の世界選手権は今までの取り組みが結実した。準々決勝以降の3試合で計276分の消耗戦。片山さんは「車で同じ距離を走っても、ガタガタしている車と、滑らかに走る車では車体へのダメージが異なる。世界選手権も、周囲のイメージより実際の疲労度は少なかった」と解説する。決勝の相手になったシンドゥ・プサルラ(インド)とはリオ五輪の準決勝でも対戦し、その時は179センチの長身からのスマッシュに屈し完敗した。だが、今年の世界選手権ではプサルラを振り回し、十分な体勢でスマッシュを打たせないことに成功した。
故障を何度も乗り越えてきた中で心境にも変化が生まれている。今、プレーができていることだけで奇跡だと思うようになった。15年に日本で開かれた国際大会以降、試合前にコートに入る際は頭を下げて目をつぶり、唱えるようになった。
「この舞台に立てることに感謝して、思い切り楽しもう」
奥原が高校3年の冬、授業で将来の目標を一枚の紙に書く機会があった。15年は<世界ランキング1桁へ>、16年は<五輪メダル獲得>、17年は<ちょっと息抜き。世界選手権優勝>と書き、本当にすべて達成してきた。
次なる目標は、世界選手権の表彰台の頂点で聞いた国歌を、東京五輪で観客と一緒に聞くこと。その開幕まで、あと約1000日。奥原に「長く感じますか? 短く感じますか?」と尋ねた。「短い」と返されるかと思ったが、違った。
「年月の流れで『もう半年だね』と言う人がいますが、私は『まだ半年』と思ったことしかない。それくらい充実して長い一日一日を過ごしている。あと1000日間も長いと思いますよ」
毎日を真剣に過ごしてきた奥原にしか言えない言葉だろう。自分が結果を残すことでバドミントンをメジャー競技にしたいと高校時代から言ってきた。自国開催の五輪は最大のチャンスでもある。ひたすらに自らを追い込む濃厚な鍛錬の1000日間が続いていく。